
コラムCOLUMN
歯周病とは?原因・症状・予防法まで徹底解説|今すぐできるセルフケアも紹介
こんにちは。岐阜市加納朝日町、JR東海道本線「岐阜駅」より徒歩10分にある歯医者「ありもと歯科」です。

歯磨きのときに出血があったり、口臭が気になったりした経験はありませんか。「たいしたことないだろう」と見過ごしがちですが、それは歯周病のサインかもしれません。
歯周病は、成人が歯を失う最大の原因でありながら、痛みなどの自覚症状がないまま静かに進行します。気づいたときには手遅れ、ということにもなりかねないため、正しい知識と早期の対策が不可欠です。
この記事では、歯周病の主な原因や進行段階ごとの症状、ご自身でできる予防法について詳しく解説します。セルフチェックの方法や全身の健康との関わりもご紹介しますので、お口の健康を長く守りたい方はぜひ参考にしてください。
歯周病とは

歯周病は、歯を支える歯ぐきや骨などの組織に炎症が生じる病気です。主な原因は、歯と歯ぐきの間に付着したプラーク(歯垢)です。この中に含まれる細菌が歯茎に炎症を起こし、歯周病が進行していきます。
初期段階では自覚症状がほとんどないため、沈黙の病気とも呼ばれています。進行すると歯ぐきの腫れや出血、口臭などの症状が現れ、最終的には歯がぐらつくなどの症状が出てきます。
歯周病は成人の多くが罹患しているとされ、放置すると歯を失うリスクが高まるため、早期のケアが重要です。
歯肉炎と歯周炎の違い
歯周病は大きく「歯肉炎」と「歯周炎」に分類されます。歯肉炎は歯ぐきだけに炎症が起こる状態で、歯ぐきの腫れや出血がみられますが、歯を支える骨には影響がありません。
一方、歯周炎は炎症が進行し、歯ぐきだけでなく歯を支える骨や靭帯にもダメージが及びます。歯周炎になると歯ぐきが下がったり、歯がぐらついたりすることがあり、治療もより複雑になります。
歯肉炎の段階で適切なケアを行うことで、歯周炎への進行を防ぐことが期待できます。
歯周病の原因と発症メカニズム

歯周病の原因と発症メカニズムについて、主な要因や体への影響をわかりやすく解説します。
歯垢(プラーク)と歯周病菌の関係
歯周病は、歯と歯ぐきの境目にたまる歯垢(プラーク)が主な原因とされています。歯垢は食べかすや細菌が集まったもので、放置すると歯周病菌が増殖しやすくなります。これらの細菌が産生する毒素が歯ぐきに炎症を引き起こし、やがて歯を支える骨や組織にも影響を及ぼすことがあります。
日々の歯磨きで歯垢をしっかり除去することが、歯周病予防の基本となります。
生活習慣や体質が与える影響
歯周病の進行には、生活習慣や体質も大きく関わっています。例えば、糖分の多い食事や不規則な生活、睡眠不足などは、口腔内の細菌バランスを崩しやすくします。
また、体質的に唾液の分泌が少ない方や免疫力が低下している場合は、歯周病菌に対する抵抗力が弱まりやすい傾向があります。
喫煙・ストレス・全身疾患との関連
喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、歯周病のリスクを高めることが知られています。
また、ストレスが続くと免疫力が低下し、歯周病菌への抵抗力が落ちる場合があります。さらに、糖尿病などの全身疾患がある方は、歯周病が悪化しやすいことが報告されています。
歯周病の主な症状と進行段階

ここでは、歯周病の主な症状と進行段階について解説します。
初期症状と見逃しやすいサイン
歯周病の初期段階では、歯ぐきの腫れや赤み、歯みがき時の出血などが見られることがあります。
しかし、痛みを伴わない場合が多く、これらのサインを見逃してしまう方も少なくありません。口臭が気になるようになったり、歯ぐきがむずがゆいと感じることも初期の兆候となることがあります。
中等度・重度の症状とリスク
進行すると、歯ぐきの腫れや出血がさらに目立つようになり、歯と歯ぐきの間に深い溝(歯周ポケット)ができることがあります。
また、歯が浮いたような感覚や、ものを噛んだときの違和感が現れることもあります。歯ぐきが下がることで歯が長く見えるようになり、歯のぐらつきが生じる場合もあります。
歯周病が進行した場合の影響
歯周病が重度まで進行すると、歯を支える骨が大きく失われ、最終的に歯が抜け落ちてしまうことがあります。また、歯周病は全身の健康にも影響を及ぼすことが指摘されています。糖尿病や心血管疾患などのリスクを高めるとされているのです。
歯周病のセルフチェック方法

歯周病は初期段階では自覚症状が少なく、気づきにくい病気です。適切なセルフチェック方法を理解し、自宅で実践して早期発見に努めましょう。
まずは、歯磨きの際に歯ぐきから出血がないかを確認しましょう。歯ぐきが赤く腫れていたり、触れると痛みを感じる場合も注意が必要です。
また、歯ぐきが下がって歯が長く見える、歯と歯の間に食べ物が挟まりやすくなった、口臭が気になるといった変化も歯周病のサインとなることがあります。鏡を使って歯ぐきの色や形状を観察し、違和感がないか定期的に確認することが大切です。
歯周病が疑われる場合は
セルフチェックで歯周病が疑われる場合は、早めに歯科医院を受診してください。自己判断で市販薬や民間療法に頼るのではなく、専門家による診断と指導を受けましょう。
歯周病の予防と日常ケアのポイント

歯周病を予防し、健康な口腔環境を保つためには、日常生活でのケアが非常に重要です。
正しい歯磨きとデンタルケア用品の選び方
歯周病予防には、歯ブラシの毛先が歯と歯ぐきの境目にしっかり届くように、やさしく小刻みに磨くことが大切です。歯ブラシは自分の口に合ったサイズや硬さを選び、毛先が開いてきたら1か月を目安に交換しましょう。
また、歯間ブラシやデンタルフロスを併用することで、歯と歯の間のプラーク除去も効果的に行えます。
食生活・生活習慣で気をつけたいこと
バランスの良い食事を心がけることが、歯周病予防につながります。特に、糖分の多い飲食物は控えめにし、よく噛んで食べることが唾液の分泌を促し、口腔内の自浄作用を高めます。
また、喫煙は歯周病のリスクを高める要因とされているため、禁煙を意識することも大切です。
歯科医院での定期検診の重要性
ご自宅でのセルフケアだけでは落としきれない歯石やプラーク(歯垢)も、歯科医院の専門的なクリーニングなら隅々まで除去できます。お口の中がさっぱりと気持ちよくなりますよ。
このプロのケアを定期的に受ける一番のメリットは、「予防」ができることです。むし歯や歯周病を早期に発見できるため、大掛かりな治療になるのを防ぎ、健康な口内環境を長く保つことができます。特に症状がなくても、半年に一度を目安にプロのチェックを受けることをおすすめします。
歯周病の治療方法と治療の流れ

歯周病の治療方法と治療の流れについて、具体的な治療内容や期間、治療後の注意点まで詳しく解説します。
歯科医院で行う主な治療法
歯周病の治療は、まず歯科医院での専門的な診査・診断から始まります。基本的な治療としては、歯石やプラーク(歯垢)の除去を目的としたスケーリングやルートプレーニングが行われます。進行した歯周病の場合には、歯周ポケットの清掃や、必要に応じて歯周外科手術が検討されることもあります。
また、歯周病の進行度や患者様の全身状態によっては、内服薬や抗菌薬の使用が提案される場合もあります。
治療にかかる期間と費用の目安
治療にかかる期間は、歯周病の進行具合によって変わります。軽度であれば数回の通院で終わることがほとんどです。症状が進んでいる場合は、数ヶ月間の治療と、その後の定期的なメンテナンスが大切になります。費用は、基本的に保険が適用されます。
ただし、外科的な処置など、より専門的な治療が必要な場合は自費となることもございます。
治療後に気をつけるポイント
治療後は再発防止のため、毎日の丁寧な歯磨きと定期的な歯科検診が重要です。生活習慣の見直しや歯科医師や歯科衛生士の指導に従ったセルフケアの継続も求められます。治療後も口腔内の状態を良好に保つことで、歯周病の再発リスクを低減することが期待できます。
歯周病と全身の健康との関係

歯周病はお口の中だけでなく、全身の健康にも大きく関わることが近年の研究で明らかになっています。
糖尿病や心疾患など全身疾患との関連性
歯周病は、糖尿病や心疾患などの全身疾患と深い関係があると考えられています。例えば、歯周病による慢性的な炎症が血糖値のコントロールを難しくする可能性があり、糖尿病の方は歯周病が進行しやすい傾向も指摘されています。
また、歯周病菌が血流に乗って全身へ広がることで、動脈硬化や心筋梗塞などのリスクが高まることも報告されています。
妊娠中の歯周病リスク
妊娠中はホルモンバランスの変化によって歯ぐきが炎症を起こしやすくなり、歯周病が悪化しやすい時期といわれています。実際に、歯周病が進行すると早産や低体重児出産のリスクが高まる可能性があることも報告されています。
そのため、妊娠中の方は特にお口の健康管理を意識することが大切です。
定期的に歯科検診を受け、歯科医師や歯科衛生士の指導を受けながら適切な口腔ケアを続けることで、ご自身の健康だけでなく、お腹の赤ちゃんの健やかな成長にもつながります。
歯周病に関するよくある誤解
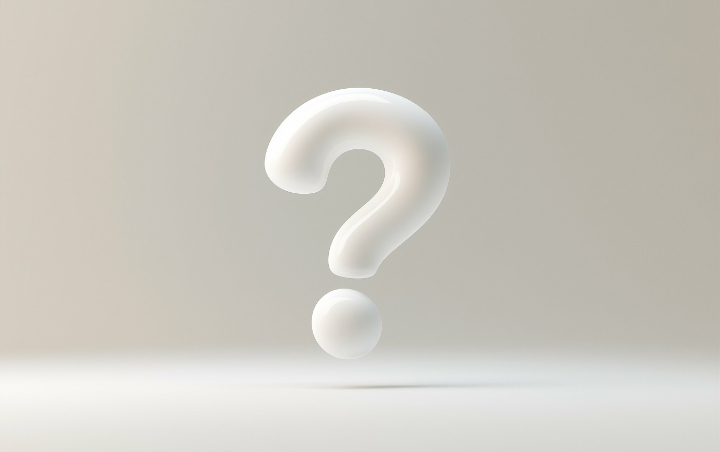
歯周病については、一般的に多くの誤解が存在します。ここでは、よくある誤解について詳しく解説します。
「痛みがない=問題ない」は本当か
歯周病は初期段階では自覚症状がほとんど現れないことが多く、痛みがないからといって健康だと判断するのは適切ではありません。
実際には、歯ぐきの腫れや出血など軽微な症状が進行している場合もあります。進行すると歯を支える骨が徐々に破壊され、最終的には歯が抜けてしまうこともあるため、痛みがなくても定期的な歯科検診が重要です。
若い人は歯周病にならない?
歯周病は中高年に多いイメージがありますが、実際には若い世代でも発症することがあります。特に、生活習慣や口腔ケアの状況、遺伝的な要因などが関係しており、10代や20代でも歯ぐきの炎症や出血が見られるケースも少なくありません。
若いからといって油断せず、日々のブラッシングや歯科医院での定期的なチェックを心がけることが大切です。歯周病のリスクを正しく理解し、予防に努めましょう。
まとめ

歯周病は、歯垢に含まれる細菌が主な原因で、自覚症状が少ないまま進行し、最終的には歯を失うリスクもある怖い病気です。
また、喫煙やストレスなどの生活習慣、さらには糖尿病といった全身の健康とも深く関わっています。
大切な歯を歯周病から守るためには、毎日の丁寧な歯磨きといったセルフケアはもちろんのこと、自覚症状がなくても歯科医院で定期的に検診やクリーニングを受けることが非常に重要です。
歯周病治療を検討されている方は、岐阜市加納朝日町、JR東海道本線「岐阜駅」より徒歩10分にある歯医者「ありもと歯科」にお気軽にご相談ください。
当院は「すべての方が安心して気軽に通える歯科医院」をコンセプトとして医院の設計や治療をご提供しております。

